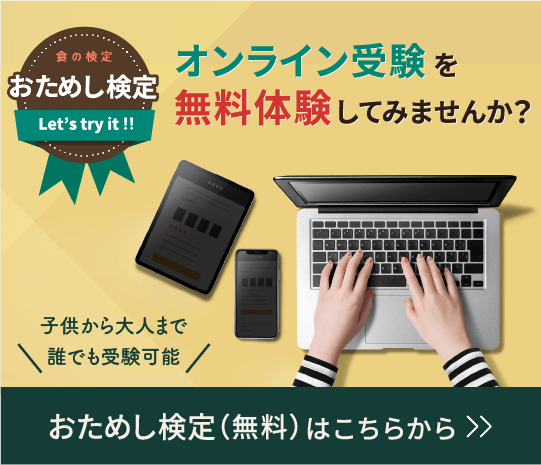急に立ち上がったとき、くらくらしたり、めまいがしたりする、これが「貧血」だと思っていませんか。これは「立ちくらみ」で、病的な場合は起立性低血圧と呼ばれます。では、貧血とはどのような状態のことなのでしょうか? 今回は、貧血についてお伝えします。
貧血とは
血液は骨髄でつくられ、酸素や栄養の運搬、病原菌などの異物の排除、傷ついた血管の修復、出血時の止血など、体にとって大切な役割を果たしています。
その血液中の赤血球は、ヘモグロビンという鉄を含んだたんぱく質を持っています。このヘモグロビンの量が少なくなった状態を貧血といいます。鉄が赤い色素を持っているため、血液は赤く見えるのです。
ヘモグロビンは、肺で酸素と結びつき、全身に酸素を運ぶ役割を担っています。全身に酸素が行き渡らないと、めまいや動悸、息切れ、疲れやすい、頭痛、集中力の低下、冷え、顔面蒼白などのさまざまな不調が現れます。
赤血球の大きさも貧血と関係しています。血液検査の項目にあるMCV(平均赤血球容積)というのが、赤血球1個当たりの大きさの指標で、小球性貧血、正球性貧血、大球性貧血に分類されます。
小球性貧血は、ヘモグロビンの産生がうまくできず、赤血球が正常より小さいケース。
正球性貧血は、赤血球の大きさは正常だが、出血や溶血、造血機能の異常などが要因となっているケース。
大球性貧血は、赤血球が大きくなっているものの、赤血球細胞をつくる過程で必要な物質が足りずに起こるもの。
貧血の種類と原因
貧血にはいくつか種類があり、原因はさまざまです。下記に、主な種類と原因を紹介します。
- 鉄欠乏性貧血
貧血の中で最も多い貧血です。小球性貧血に分類されます。ヘモグロビンを構成する「鉄」が不足して起こります。偏食や小食による鉄の摂取不足、月経や消化管からの出血の持続、胃腸切除による吸収低下などがあります。成長期や妊娠・授乳により鉄の需要が増加するケースも挙げられます。
- 溶血性貧血
赤血球が破壊され、造血が追いつかずに赤血球数が少なくなることで起こる貧血です。正球性貧血に分類されます。原因はいくつかありますが、一番多いのは、赤血球を壊す免疫がつくられてしまうこと。ほかに、激しい運動で足の裏に強い衝撃がかかり続け、赤血球が破壊されて起こることもあり、スポーツ貧血とも呼ばれたりします。
- 巨赤芽球性貧血
ビタミンB12や葉酸の不足で起こる貧血です。大球性貧血に分類されます。ビタミンB12や葉酸は赤血球をつくる細胞のDNA合成を助けてくれる栄養素であるため、不足するとDNA合成がうまくいかず、ヘモグロビンの数が減って貧血が起こります。胃切除後、萎縮性胃炎などに伴うビタミンB12欠乏、アルコール多飲、栄養不良に伴う葉酸欠乏も原因として挙げられます。
- 再生不良性貧血
骨髄で血液がつくられないため、血液中の赤血球や白血球、血小板のすべての血球が減ってしまう病気で、国が指定する難病の対象です。
- 腎性貧血
腎臓はさまざまなホルモンを分泌しています。その中に赤血球をつくる働きを促進してくれるエリスロポエチンというホルモンがあります。腎臓の機能が低下すると、そのエリスロポエチンの分泌が減ってしまうため、赤血球をつくる力が低下して貧血となります。これを腎性貧血といいます。
貧血といってもさまざまな種類、原因があることがおわかりいただけたと思います。次回は貧血の中でも最も多い「鉄欠乏性貧血」の予防についてお伝えします。
【参考文献】
・e-ヘルスネット「鉄」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-022.html
・国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
https://www.ncgg.go.jp/hospital/navi/11.html
ライター:山下 真澄
管理栄養士|日本スポーツ協会公認スポーツ栄養士|
食育インストラクター|一級惣菜管理士|調理師




 シェア
シェア ツイート
ツイート