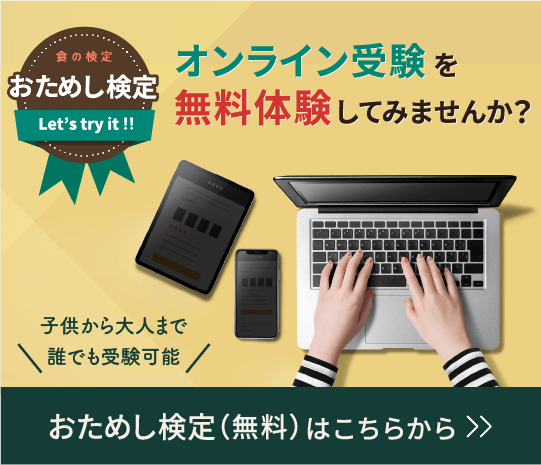前回は貧血の病態や種類・原因などについてお伝えしました。今回は貧血のなかでも最も多い「鉄欠乏性貧血」についてお伝えします。
鉄欠乏性貧血とは
鉄欠乏性貧血は、貧血のなかで最も多い貧血で、成人女性の約25%が発症しているといわれています。ヘモグロビンを構成する「鉄」が不足して起こります。
原因は、前回もお話ししたとおり、偏食や食べる量が少ないことによる鉄の摂取不足、月経や消化管からの出血の持続、胃腸切除による吸収低下などがあげられます。成長期や妊娠・授乳によって鉄の需要が増加することでも鉄の不足が起きます。
アスリートに多い貧血も、このタイプの貧血です。アスリートは筋肉量が多いため、その筋肉量に見合うだけの鉄が必要となります。さらに、練習や試合で多くの汗をかくことによって、汗の中に含まれている鉄が失われます。競技によっては体重をコントロールする必要があり、それに応じて食事制限をすることで鉄の摂取不足になります。特に女性アスリートは、月経との兼ね合いもあるため、鉄が不足しやすくなります。
鉄欠乏性貧血の症状
鉄は全身への酸素運搬という重要な役割を担っているため、鉄が不足すると全身の細胞に酸素が行き渡らず、組織や臓器にさまざまな悪影響を及ぼします。疲れやすい、だるい、動悸、息切れ、めまい、耳鳴り、顔色が悪い、眼瞼結膜の蒼白、さじ状爪、口内炎、異食症などなど。特にアスリートの場合、貧血になることはパフォーマンスに影響します。
疲れやすい、だるいなどの症状は、日ごろ、仕事で忙しくしているときでもよくあること。ついつい「いつものこと」と、そのままにしがちです。しかし、そのような状態が長く続く場合は、鉄欠乏性貧血の可能性も視野に入れ、医療機関の受診をお勧めします。放っておくと大きな病気を引き起こす可能性もあります。
鉄欠乏性貧血は、ヘモグロビンの量で診断されます。WHOの基準では、男性13g/dL、女性12g/dL未満を貧血と定義しています。貧血はさまざまな要因で起こるため、ヘモグロビン値だけではなく、赤血球指数や血清フェリチンなども参考とされます。
予防と改善の食事の基本
鉄欠乏性貧血の予防には、「鉄」の摂取が重要になります。食品中の鉄は、「ヘム鉄」と「非ヒム鉄」に分けられます。ヘム鉄は、主にレバーや赤身肉、青魚などの動物性食品に多く含まれています。非ヘム鉄は、主に大豆製品や青菜、海藻などの植物性食品に含まれています。
鉄は吸収されにくい栄養素ですが、ヘム鉄と非ヘム鉄の吸収率は違います。どちらかといえば、非ヘム鉄のほうが吸収されにくく、さらに緑茶やコーヒーに含まれるタンニンと結合すると吸収が阻害されてしまいます。ヘム鉄は非ヘム鉄より吸収率が高く、ほかの食品の影響を受けません。とはいえ、ヘム鉄、非ヘム鉄、どちらもバランスよく摂るのがベストです。
貧血予防・改善には、鉄ばかりではなく、ほかの栄養素も必要です。特にビタミン類は貧血とは、切っても切れない関係にある栄養素です。例えば、ビタミンB6はヘモグロビンの合成に関わり、ビタミンB12・葉酸は骨髄で正常な赤血球をつくる役割を、ビタミンCは鉄の吸収を高める働きをしています。動物性たんぱく質も鉄の吸収を高めてくれるので、鉄と一緒に摂ると貧血解消に役立ちます。
ポイントは…
- 1日3食、主食・主菜・副菜が並ぶバランスのよい食事を心がける
鉄は、不足しがちな栄養素です。そのため1食でも欠食すると、ますます不足してしまいます。毎日3食、バランスよく食べることで鉄欠乏を防ぎましょう。
- 鉄の多い食品を意識して摂る
ヘム鉄と非ヘム鉄をバランスよく摂りましょう。意識して摂らないと不足してしまう恐れがあります。鉄を多く含む食品は、レバーや鮎、鰯、貝類、のり、ひじき、がんもどき、納豆、油揚げ、パセリ、小松菜、枝豆、ほうれん草など。
- 鉄の吸収を高める食品と一緒に!
鉄は吸収率が低いので、吸収を高める食品と一緒に摂りましょう。ビタミンCは、ほうれん草やブロッコリー、パプリカ、じゃがいも、オレンジ、グレープフルーツ、キウイフルーツ、いちごなど、色の濃い野菜や柑橘類に多く含まれています。たんぱく質は、肉や魚、大豆製品、卵などに多く含まれています。主菜となる栄養素なので、毎食必ず食べるようにしましょう。
鉄は不足しがちな栄養素であり、吸収率も悪いため、意識して摂ることや吸収を高める食品と一緒に摂ることが大切です。食後の緑茶やコーヒーは吸収を阻害してしまうため、飲むときは少し時間をおいてから飲むといいでしょう。鉄を意識して摂ることはなかなか大変かもしれません。サプリメントを使うのも一つの手ですが、長期にわたり過剰に摂取し続けると、胃腸障害・便秘などの副作用が出る場合があるため注意が必要です。
【参考文献】
・鉄欠乏性貧血の検査と診断
日内会誌. 2010;99(6);1213-1219
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/99/6/99_1213/_pdf
ライター:山下 真澄
管理栄養士|日本スポーツ協会公認スポーツ栄養士|
食育インストラクター|一級惣菜管理士|調理師




 シェア
シェア ツイート
ツイート